転職を考える際、現在の会社を退職する手続きに不安を感じる方は多いはずです。正しい退職手続きの流れを知っておかないと、手続きがスムーズに進まず退職までに時間がかかってしまいます。この記事では、退職の意思表示から退職当日までの流れ、会社とやり取りする書類、退職後に必要な公的手続きを解説します。
記事を読めば退職までの流れが明確になるため、迅速な退職準備が可能です。トラブルを避け、退職後の新しいスタートをスムーズに切りましょう。
退職手続きの流れ

退職手続きの流れは以下のとおりです。
- 退職の意思を伝える
- 退職願・退職届を提出する
- 業務を引き継ぐ
- 取引先にあいさつする
- 有給休暇を消化する
- 退職当日の対応をする
1.退職の意思を伝える
退職を決意したら、直属の上司に退職の意思を伝えましょう。退職したい意思の伝え方によって、その後の手続きがスムーズになります。退職したい日の1〜3か月前までには、退職の意思を上司に伝えてください。退職の意思は、平日の業務時間内に直属の上司へ伝えることが重要です。
退職の意思は「一身上の都合により○月○日付で退職させていただきたいと考えています」と明確に退職日を伝えます。退職の理由を聞かれた場合は「キャリアアップのため」など、ネガティブな表現を避けて答えましょう。
2.退職願・退職届を提出する
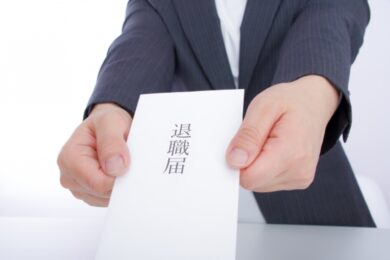
退職の意思を上司に伝えたら、次は退職願や退職届を提出しましょう。退職願と退職届は似ていますが、役割が異なります。退職願は退職の意思を表明する文書です。退職願に法的な義務はなく、会社内の慣例として提出するものです。退職願の宛先は直属の上司にしましょう。
会社によっては、退職願の代わりに退職届を直接提出する場合もあります。退職届は法的に有効な文書です。退職届は就業規則に定められた期間内(通常1〜2か月前)に提出しましょう。退職届の宛先は社長や代表取締役にしてください。退職日は給与計算や社会保険手続きの都合により、月末にすることが一般的です。
退職届には「一身上の都合により」などの退職理由を簡潔に記載します。詳細な退職理由を退職届に書く必要はありません。退職届は基本的には手書きを推奨しますが、会社指定のフォーマットがある場合は従いましょう。退職届が受理されたらコピーを保管しておきましょう。
3.業務を引き継ぐ
退職届を提出したら、後任の担当者に業務の引き継ぎを行います。退職前の引き継ぎは後任者の負担を減らし、円満な退職につながります。業務を引き継ぐ際は、上司と相談して引き継ぎ期間を決めましょう。退職前の引き継ぎは一般的に2週間から1か月程度の期間が必要です。引き継ぎ作業の一例は、下記のとおりです。
- 引き継ぎ書を作成する
- 定期・不定期業務を区別する
- 業務をマニュアル化する
- プロジェクト状況を文書化する
- デジタルデータを整理する
- アカウントやパスワードの引き継ぎリストを作成する
- 業務に必要なアクセス権限を移行する
後任者とは直接対面して説明する機会を設けましょう。文書だけでは伝わらない業務のコツも共有できます。退職後の引き継ぎを行う際は、過去のトラブル事例と解決方法も伝えましょう。過去のトラブル事例がわかれば、後任者が同じ問題に直面したときに役立ちます。
4.取引先にあいさつする

取引先との良好な関係を維持するためには、あいさつをきちんと行うことが大切です。取引先への退職あいさつは、基本的には直接訪問しに行ってください。取引先に時間的な制約がある場合は、電話や手紙での対応も可能です。退職日の1〜2週間前を目安に、退職のあいさつの計画を立てましょう。
取引先に退職のあいさつをする際は、上司や先輩と訪問し後任者を紹介しましょう。取引先には簡単なあいさつと今までの感謝を伝えます。取引先との会話では個人的な連絡先は基本的に教えず、転職先について詳しく話さないようにしましょう。取引先との会話中は、現在の会社の悪口は絶対に言わないことが重要です。
5.有給休暇を消化する
退職前に残っている有給休暇を消化すれば、給料をもらいながら次の就職活動や心身の休息に時間を使えます。有給休暇は労働者の権利として法律で保障されているものです。退職前に残りの有給休暇日数を人事部や上司に確認しましょう。有給休暇の消化方法は、主に下記のとおりです。
- 退職日直前にまとめて連続消化する
- 退職日までに分散消化する
有給休暇消化の希望を伝える際は、業務に支障が出ないよう2週間から1か月前に上司に相談することがマナーです。後任者に業務の引き継ぎを完了してから、有給休暇の消化に入りましょう。会社によっては退職前の有給休暇の消化を認めない場合もあります。
事前に就業規則を確認し、有給休暇の消化が認められない場合は買取制度があるか確認してください。有給休暇の消化中は社員としての身分が継続します。就業規則に違反する副業などは避け、休暇中の連絡手段は事前に上司や同僚と決めておきましょう。
6.退職当日の対応をする
退職当日は、会社との最終的な区切りをつける大切な日です。退職当日は丁寧に対応すれば、退職後に気持ちよく次のステップに進めます。退職当日には会社の備品返却や私物の整理、最終書類の確認、同僚へのあいさつを行います。
社用携帯やパソコンは初期化が必要な場合があるので、事前に上司に確認しましょう。退職する際は、会社の機密情報を絶対に持ち出さないよう注意が必要です。自分の机やロッカーの私物は、退職前にすべて整理して持ち帰ります。必要なデータのバックアップを取りたい場合は、会社のルールに従ってください。
退職当日は、会社メールや社内システムからも忘れずにログアウトしましょう。書類関係では、退職に関する最終確認書類へのサインや最終勤怠記録の確認・提出を行います。退職金や最終給与の支払い時期・方法についても確認しておきましょう。退職証明書などの必要書類も忘れずに受け取ります。
同僚や上司へあいさつする際は、業務に関する質問事項がある場合に備え、連絡先を伝えておきましょう。退職当日の対応は忙しくなりがちなので、チェックリストを作っておくことをおすすめします。
退職手続きで会社に提出・返却するもの
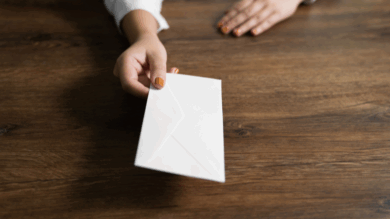
退職手続きで会社に提出・返却するものは下記のとおりです。
- 退職届
- 支給されたもの・資料
退職届
退職届は単なる形式ではなく、法的にも有効な意思表示となるためきちんと作成しましょう。退職届に記載すべき項目は、下記のとおりです。
- 日付
- 宛先
- タイトル
- 退職日
- 氏名
- 印鑑
退職届には任意で簡潔な退職理由やお礼の言葉を記載しても問題ありません。
支給されたもの・資料
会社から支給されたものや資料は、退職時にすべて返却する必要があります。退職時に返却が必要な主なものは、下記のとおりです。
- 名刺
- 社員証
- 制服
- 通勤定期券
- 健康保険証
- 社員手帳
- 業務用携帯電話
- パソコン
- タブレット
- アクセスカード
- 鍵
- 会社のクレジットカード
- 社用車
- 取引先の入館証
- 研修資料
- マニュアル
- 顧客情報
あらかじめリストを作成して退職までに計画的に返却するとスムーズに進みます。
退職手続きで会社から受け取るもの

退職手続きで会社から受け取るものは、下記のとおりです。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 退職証明書
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険への加入を証明できる書類です。新しい会社に入社する際、雇用保険被保険者証を提出することで、これまでの雇用保険の被保険者期間が通算されます。雇用保険被保険者証は、退職後10日以内に会社から交付されることが一般的です。
雇用保険被保険者証を受け取ったら内容に誤りがないか確認し、記載内容に誤りがある場合は速やかに訂正を依頼しましょう。何らかの理由で雇用保険被保険者証受け取れなかった場合は、ハローワークで再発行が可能です。転職先が決まっていない場合は、雇用保険被保険者証と離職票を使って失業給付の手続きを行いましょう。
年金手帳
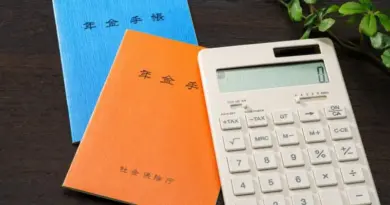
年金手帳も退職時に必ず会社から返却を受ける必要がある書類です。年金手帳は転職先での年金加入手続きに必要なため、会社が預かっている場合は必ず返却を求めてください。年金手帳を紛失してしまった場合は、最寄りの年金事務所で再発行の手続きが必要です。
2022年4月以降、年金手帳は「基礎年金番号通知書」に変更されています。マイナンバーカードを持っていれば、年金手帳がなくても手続きできる場合があります。
源泉徴収票
退職時には必ず会社から源泉徴収票を受け取りましょう。源泉徴収票は、1年間の給与支払額と所得税の源泉徴収額を証明する重要な書類です。会社には、1月1日から退職日までの期間について源泉徴収票を発行する義務があります。源泉徴収票は、退職時か年末調整後(翌年1月末まで)に受け取れます。
源泉徴収票に記載されている情報は、下記のとおりです。
- 給与・賞与の総支給額
- 各種保険料の支払額
- 所得控除の金額
- 源泉徴収された税額
年の途中で退職した場合は、源泉徴収票を使って確定申告することで所得税が還付される可能性があります。確定申告は払いすぎた税金が戻ってくるチャンスなので、ぜひ活用しましょう。源泉徴収票を紛失しても再発行が可能です。源泉徴収票の再発行には手間がかかるため、退職後5年間は保管しておくことをおすすめします。
離職票

離職票は失業給付(失業保険)を受け取るために必要な書類です。離職票には「離職票1」と「離職票2」の2種類があります。離職票1には個人情報や離職理由などの基本情報が、離職票2には賃金支払い状況や被保険者期間が記載されています。
離職票の発行は通常1〜2週間程度かかることが一般的です。会社は離職者の退職後10日以内にハローワークへ書類を提出します。ハローワークから会社に離職票が交付され、離職者に渡されます。離職票に記載される離職理由が会社都合か自己都合かによって、失業給付の給付制限期間や給付日数が変わるため注意が必要です。
自己都合退職の場合は原則として3か月の給付制限期間があります。会社都合退職の場合は7日間の待機期間後すぐに給付が開始されます。離職票を紛失してしまった場合、ハローワークで再発行が可能です。離職日の翌日から1年以内に手続きをしなければ、失業給付の受給権が消滅してしまうので注意しましょう。
退職証明書
退職証明書は在職期間などを示す公的な書類です。退職証明書は労働基準法第22条にもとづいて発行されます。転職活動や各種手続きの際に退職証明書が必要です。退職証明書には、下記の項目から必要なものだけを選んで請求できます。
- 使用期間
- 業務の種類
- 事業における地位
- 賃金
- 退職の事由
転職先に給料のことを知られたくない場合は、賃金の項目を除いての請求も可能です。退職証明書を退職後に請求すると、発行までに時間がかかる場合もあるため注意しましょう。
» 転職活動の平均期間と期間を短くするコツを紹介!
退職後に行う公的な手続き

退職後に行う公的な手続きは下記のとおりです。
- 健康保険の手続き
- 雇用保険(失業保険)の申請
- 年金の切り替え
- 住民税・所得税の確認
健康保険の手続き
退職後に重要な手続きの一つが健康保険の切り替えです。会社を退職すると加入していた健康保険の資格を失うため、新たな健康保険に加入しなければなりません。退職後の健康保険には主に次の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険へ加入する
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 家族の扶養に入る
国民健康保険に加入する場合は、会社の健康保険資格を失ってから14日以内に居住する市区町村役場で手続きをしてください。国民健康保険に加入する手続きには健康保険資格喪失証明書や本人確認書類、マイナンバーカード(通知カード)が必要です。
任意継続被保険者制度は、退職後も最長2年間元の健康保険を継続できる制度です。任意継続被保険者制度の保険料は会社負担分も含めて全額自己負担になるため、費用が増加します。任意継続被保険者制度を利用するには、退職日から20日以内に申請しましょう。
年収130万円未満などの条件を満たせば、配偶者の健康保険に扶養家族として加入できます。配偶者の健康保険へ加入する場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きを行ってください。
雇用保険(失業保険)の申請
雇用保険(失業保険)の基本手当は、失業中の生活を支えるための給付金です。雇用保険の申請は最寄りのハローワークで行いましょう。雇用保険は退職後すぐに申請可能です。原則として離職後7日間の待機期間を経てから、雇用保険の給付金を受け取れます。
自己都合で退職した場合、雇用保険には3か月の給付制限期間があります。会社都合による退職の場合は、雇用保険の給付制限期間はありません。雇用保険の基本手当の金額は、離職前6か月の賃金をもとに計算されます。雇用保険の給付日数は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由によって90〜330日の間で変動します。
年金の切り替え

退職後には年金の切り替え手続きも必要です。年金の切り替え手続きを怠ると将来の年金受給額に影響します。退職後の転職先が会社員の場合、退職時に年金手帳を返却してもらい、新しい会社に年金手帳を提出しましょう。新しい会社側が厚生年金の加入手続きを行います。
会社員から自営業に転職する場合は、国民年金への切り替えが必要です。退職後14日以内に居住地の市区町村で、国民年金への切り替え手続きを行いましょう。厚生年金から国民年金に切り替わると、保険料が全額自己負担になります。経済的に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度を利用できます。
住民税・所得税の確認
退職後も税金の支払いは続くため、住民税と所得税の確認を行いましょう。住民税は前年の所得にもとづいて計算されるため、退職後も支払い義務があります。住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類です。
退職すると給料から天引きされていた「特別徴収」から、自分で納付する「普通徴収」に切り替わることが多くあります。退職後に市区町村から住民税の納付書が送られてくるため、期限内に支払いましょう。退職時に所得税の未払い分がある場合は確定申告が必要です。
まとめ

退職する際は退職の意思表示から当日の対応まで各段階を確認し、事前に必要書類を整えましょう。退職の手続きには退職理由や退職日、引き継ぎ業務など、念入りに計画を立てて行動することが求められます。退職手続きのチェックリストを作っておけば、抜け漏れを防ぎスムーズに退職できます。
退職後の公的手続きや失業保険の申請、年金の手続きも忘れずに行うことが大切です。万全の準備を整え、退職後に気持ちよく新たなスタートを切りましょう。
» 転職活動の基本まるわかり!